「“テイスト・オブ・ジャパン”を武器に、米国でも加工食品製造を一大事業に育てる」
さまざまなフィールドで未来の創造に挑むニッポンハムグループの社員が語る本連載「挑戦者たち」。今回紹介するのは、海外事業本部事業統括部北米担当の執行役員として、米国の現地法人「デイリーフーズ」の代表取締役社長として指揮を執る藤井秀樹。人種や宗教など多様性に満ちた製造現場で、日本流の品質管理を徹底。オリジナルブランドの商品に対する評価を高め、取り扱い店舗数を急増させている。その挑戦に迫ります。

デイリーフーズ 藤井秀樹(ふじい・ひでき)・代表
1990年日本ハム株式会社に入社。加工事業本部デリ商品部などの部門を経て、海外戦略部長に就任。2013年4月から執行役員、その後、海外事業本部アジア・欧州事業部長などを歴任し、21年より現職。
「テイスト・オブ・ジャパン」を旗印に、新しい挑戦に乗り出したニッポンハムグループの現地法人が米国にある。カリフォルニア州サンタフェスプリング市に本拠地を置くデイリーフーズだ。2021年にデイリーフーズの代表に就任した藤井秀樹は、日本企業ならではの"妥協なきおいしさの追求"を武器に、同社の加工食品を全米の大手食品スーパー各社に広く流通させる一大チャレンジに取り組んでいる。
パンデミックによる内食需要拡大の中、攻勢に転じる
──私たちデイリーフーズが挑戦のキーワードに掲げる「テイスト・オブ・ジャパン」を直訳すれば「日本の味」。ただ当社が提供するのは、単なる日本食ではありません。この場合のテイストとは、センスや好みといった意味です。「最大限のおいしさを作り出す」というミッションに向け、品質の向上や改善にあらゆる面から取り組む日本ならではのクオリティコントロールのことを、私たちはテイスト・オブ・ジャパンと呼んでいます。 商品の完成度を高めるため、決して妥協せず細かい部分にも心血を注ぐ。そうした味への挑戦は、日本人にとっては当たり前のこと。ただ米国では、この当たり前が競合との違いを生み、顧客の満足度を高める武器となり得るのです。
デイリーフーズの創業は1977年。西海岸の日本食レストランへの食材配送を皮切りに事業を多角化してきた、ニッポンハムグループの海外現地法人第一号だ。
──当社の事業の柱は現在、次の3つです。1つ目は、米国、メキシコ、カナダなどで調達した豚肉や牛肉などの精肉を、主に日本に送る輸出事業です。 2つ目が、祖業でもある飲食店への卸業。当社所有の40台のトラックを駆使し、西海岸エリアに点在する1500軒余りのアジア系飲食店などに、水産物や日本の食材を日々配送しています。 そして3つ目が、一般消費者向けの自社ブランド品や、食品スーパー向けのPB(プライベートブランド)商品を企画製造する加工食品事業で、自社ブランドの主力は餃子と鶏のから揚げタイプの商品です。近年、特に力を入れているのがこの分野。当社のオリジナルブランド「クレイジー クイジーン」の調理済み冷凍食品「Mandarin Orange Chicken」(以下、MOC)が人気となり、米国の"メインストリーム"での売り上げが拡大しているためです。


デイリーフーズが米国の"メインストリーム"と呼ばれる大手スーパーチェーン向けに販売する加工食品。フライドチキンと餃子が主力
「オレンジチキン」というのは、鶏のから揚げに甘酸っぱいオレンジ風味のソースを絡めた米国生まれの中華料理。米国の多くの食品メーカーが製造にしのぎを削る調理済み冷凍食品の定番アイテムだ。
そして"メインストリーム"とは、日系やアジア系といったこれまでの同社の主要顧客にとらわれない、全米規模の大手スーパーチェーンや会員制大型スーパーチェーンを指す。
──デイリーフーズがMOCの製造を開始したのは今から17年前。地道な営業活動が実り、西海岸の複数のメインストリームにMOCの販売コーナーを持てるようになったものの、他社メーカーのオレンジチキンに知名度で劣り、販売実績を伸ばせずにいました。
それを一変させたのが、コロナウイルスによるパンデミックでした。飲食店が軒並み閉店するなか、自宅で簡単に食べられる調理済み食品の需要が一気に高まり、他社メーカーの冷凍食品が品薄になったのです。食に対して保守的で、食べ慣れないブランドには簡単には手を伸ばさないとされる米国の消費者でしたが、そうした状況下でMOCを試し買いしてくれるようになりました。するとそのおいしさに納得。何度もリピート買いするようになり、一時は製造が追いつかなくなるほどヒットしました。 その人気はパンデミック収束後も衰えず、MOCの売り上げは年を追うごとに増えています。この状況下でMOCが大きく飛躍できた背景には、当社ならではのテイスト・オブ・ジャパンという価値観があったから、と私は考えています。
"おいしさを最大化するための挑戦"が、売り上げ拡大に貢献
おいしさとは、味はもちろん、見た目、香り、歯ごたえ、咀嚼時の心地良い音といったさまざまな要素から成り立つ。それらを満たした"最大限のおいしさ"を実現するため、テイスト・オブ・ジャパンを実現するための「こだわり」とも言えるような配慮は、原料の選定や調達、製造、包装にいたるすべての段階に及ぶ。年間を通して同じおいしさを作り出すため、素材の選び方や、その素材をカットする際の最適な大きさ、調理温度などをデータ化して順守する一方で、湿度や気温の違いを踏まえ、季節ごとに材料の混ぜ方などを微妙に調整することもあるという。
ではMOCにおける"最大の武器"とは何か? 藤井はそれを「加熱の製法」だと断言する。
──私の知る限り、オレンジチキンを製造する米国のすべてのメーカーが、チキンを中まで火を通すためにスチームをします。スチームすると衣が水分を帯び、せっかくのクリスピーさが損なわれてしまいがち。ただスチームによる加熱は肉を縮ませにくいため、完成したチキンの見た目は相応のボリューム感が残せます。
これに対し当社はチキンをスチームせず、仕上げる際に企業秘密のある調理法を採用しています。この調理法だと手間も時間もかかり、かつボリューム感は目減りしてしまいますが、肉のしっとりした食感と、カリカリとした衣のクリスピーさは別格です。 コスト追求に走りすぎず、おいしさを最大化するこの製法を、当社は長年貫いてきましたが、ずっと、それを知ってもらえるすべがなかった。ただ、それを手に取って食べてもらえる機会を得たことで、テイスト・オブ・ジャパンが生み出すMOCのおいしさがダイレクトに消費者に伝わり、繰り返し買ってもらえるようになったのです。某有名メーカーのオレンジチキンとMOCとを食べ比べ、「衣を含めた肉そのもののおいしさはMOCが上」と評価するYouTube動画が投稿されたのも、その表れだととらえています。
"メインストリーム"におけるMOCの売り上げは、パンデミック前後で倍増し、その後の販売も堅調です。例えばある大手量販チェーンでは、パンデミック前にMOCを販売していたのは全米でも西海岸中心でしたが、24年には全米まで拡大。中でも一番伸びているのは、保守的な層が多いことで知られる中西部です。テイスト・オブ・ジャパンに沿った商品作りを行えば、保守的と言われる人々の胃袋であってもがっちりつかめるとわかり、大きな自信を得られました。
グループのネットワークを駆使し、迅速な商品開発につなげる
自社ブランドのMOCをヒットさせた藤井は、加工食品事業の柱をより太くすべく、"メインストリーム"各社に向け、PB商品の積極的な提案にも乗り出している。その一例が、「ベトナム産オーガニックしいたけ」の天ぷらだ。全米に店舗を持つアッパーミドル層をターゲットとした某大手スーパーチェーンへの納品が決まった。
──同チェーンの主要顧客は、一定の収入があり、異文化の食や健康への意識も高いとされるミレニアル世代(1980年代から90年代半ばまでに生まれた世代)。オーガニックしいたけの天ぷらなら、いかにもこの層が好みそうだと思いました。

気温が低い早朝に収穫し、午前中のうちに決められた温度・方法で揚げ、直後に急速冷凍する。この一連の流れをルール化し、現地にあるニッポンハムグループの協力工場に製造を依頼。完成品を同大手スーパーチェーンのバイヤーに試食してもらうと、風味のよさも歯ごたえも、ふつうのしいたけの天ぷらとはまったく違うと太鼓判を押されました。
提案先の客層、地域性、トレンドなどを踏まえ、PB商品のコンセプトを決定したら、おいしさを最大化すべく、原料や製法などをあらゆる側面から吟味する。それがテイスト・オブ・ジャパンの製造モデルです。この製造モデルは一種の「テンプレート」であるため、どんな商品にも応用が利きます。
このモデルが実現できるのも、原料調達や製造において、幅広い食品を製造するニッポンハムグループのネットワークをフル活用できるからこそ。世界中から最も適した食材を調達できる上、当社工場では製造が難しい場合、世界各地に点在するニッポンハムグループの拠点工場などに協力を依頼できます。こうしたアドバンテージがあるから、ハイレベルなPB商品をスピーディに作り出すことが可能なのです。
米国の"メインストリーム"は店舗数が膨大なうえ、一度「パートナー企業」と認められれば長期間、PB商品の製造をまかせてもらえるケースが多い。どのエリアにどんな魅力的な食材があり、どの程度のコストで調達できるのか。各拠点工場や協力工場はどんな加工技術を持っているのか。長年、海外事業本部に在籍する中で蓄えた情報を一元化し、今後のPB商品作りに生かしていくつもりです。
ボトムアップが、ユニークな商品開発を進めるカギに
代表就任からまもなく4年、藤井が全従業員に繰り返し呼び掛けてきたのが、「どんな意見やアイデアも遠慮せずに伝えてほしい」というメッセージだ。実際、話しやすい雰囲気を醸成するため、ふだんから社長室の扉を開けておいたり、藤井自ら従業員のもとに日々足を運んで、会話をするなど心がけている。ボトムアップを重んじるのは、「トップダウンからは、トップの頭の中にあるもの以上のアイデアは生まれないため」と藤井は言う。
──米国は世界最大の移民国家。彼らが持ち込む多様な文化が、国力の源となってきたのは誰もが認めるところでしょう。多様性へのリスペクトは食の分野でも強まっており、"メインストリーム"の総菜売り場は、「イノベーティブ・フュージョン」と呼ばれる、自由な発想から生まれた国籍やジャンルの枠を越えた料理であふれています。
デイリーフーズの従業員は現在約430名。従業員にはヒスパニック系やアジア系も多い。この人種的な多様性が持つ「文化の力」を商品開発に生かさない手はありません。
今、あるヒスパニック系従業員の意見を取り入れ、商品化を進めているのが「新感覚の無国籍餃子」です。デイリーフーズでは創業時から日本式の餃子をアジア系レストランなどに卸してきました。ただ日本式の餃子は業務用としては安定した需要があるものの、正統派すぎて業務用途以外の広がりに欠けるのではと懸念しています。そこで、"メインストリーム"にもフィットするユニークな餃子を作れないかと考えていたある時、従業員たちと食事の話になりました。そこで先のヒスパニック系従業員が「うちは3食餃子の日もあるよ」と切り出したのです。
彼いわく、ヒスパニックにとって餃子の皮は、具をラップするための主食食材としておなじみだそう。どう食べるのか聞くと、「朝食ならパワーがつくようスクランブルエッグとソーセージを巻いて焼き、ケチャップをかける」「昼食であれば腹持ちのよさを重視し、豚骨スープを絡めた麺を包んで蒸す」「夕食には、バルサミコ酢で甘みをつけた細切り牛肉を包んでグリルし、おしゃれな主菜にする」といった具合です。
これだけ驚きや楽しさにあふれた多様性のあるメニューは、日本人である私には到底思いつきません。トップダウンを排し、ボトムアップに徹したからこそ出てきたアイデアだと感じています。
──2025年から米国南東部のジョージア州と米国北西部アイダホ州に生産拠点をもつ鶏肉加工会社が新たにデイリーフーズのグループに入ります*。これにより全米への安定供給が可能になりました。パンデミックのさなか、急増するMOCの注文を既存の工場だけではさばききれず、欠品を出してしまった悔しさは今も頭を離れません。MOCをはじめとする自社ブランド商品と、"メインストリーム"向けのPB商品の製造能力を高めることが不可欠でした。これからは、東部や南部エリアにも攻勢をかけたいですし、いずれは日本やヨーロッパ、そして東南アジアにも進出したいです。テイスト・オブ・ジャパンをより洗練させ、エリアごとのニーズや客層にマッチした商品を開発できれば、決して不可能ではないでしょう。

西海岸エリアを中心に現在6カ所の拠点に加え、アイダホとジョージアにある鶏肉加工などを手がける企業グループを子会社化し、供給体制を強化した
飲食店への卸業と加工食品事業を合わせた売り上げは、2019年の1億5000万ドルから、22年には2億ドルにジャンプアップしました。勢いを駆り、2026年までに加工食品事業単体で3億ドルを売り上げるのが現時点の目標です。「デイリーフーズで働けるのはエキサイティングだ」と言ってくれる従業員たちの力を結集し、ぜひ達成したいと思っています。
─ 最後に質問です。藤井さんにとって挑戦とは? ―

デイリーフーズの社長に就任する前は、ニッポンハムグループの国際事業全般を見る立場にいました。その時から感じていたのが、私たちが、おいしさのために追求すべきと「当たり前」のように考え、行動していることが、世界基準で見ると決して「当たり前ではない」ということです。
今回お話ししたような、朝採れしいたけをフレッシュなまま加工・冷凍する工程や、MOCの製造時にひと手間加えること。これらはすべてニッポンハムグループの品質基準からしたらそこまで特別なことではありません。おそらくグループの生産現場では、常に誰かがこうしたおいしくするための工夫を、当然のようにしているでしょう。でも、そうした日々の工夫の数々は、場所を変えると決して当たり前なことではなく、ほかのどこにもない特別な価値になるのです。
そんな食への想いと知恵を世界中に知らしめるのが、私の役目だと思っています。まずは最もトレンドに敏感な米国のアッパーミドル以上の層を掴み、いずれは世界中に、ニッポンハムグループの食を伝えていきたいと考えています。
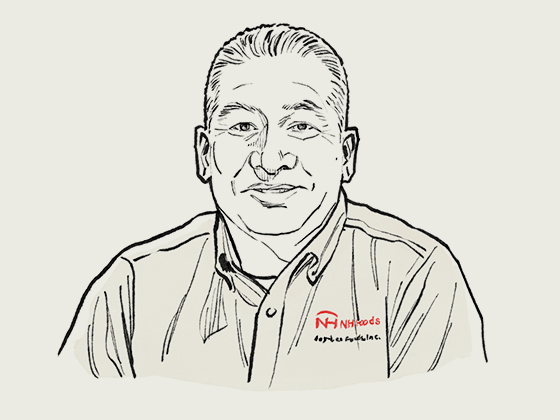
「グループが誇る『おいしい食への探究心』を世界に伝えること」です。 藤井秀樹



