社長メッセージ
新たな成長ステージを歩み始めたニッポンハムグループは
さらなる企業価値向上を目指します

代表取締役社長
「中期経営計画2026」初年度の振り返り

2024年度にスタートした「中期経営計画2026」のもと、「構造改革」「成長戦略」「風土改革」を三位一体で推進し、ビジネスモデルの変革に取り組んできました。
2025年3月期の業績は、売上高13,706億円(前期比+5.1%)、事業利益425億円(前期比△5.3%)となりました。売上高は計画通りでしたが、事業利益は中計策定後に新たに顕在化した課題に対応しきれず期初計画から55億円下回る結果となりました。しかし、全社戦略については、ほぼ順調に推移しており、これまで取り組んできた加工事業本部の構造改革やブランド戦略の効果が発現したほか、ボールパーク事業の成長もあり、骨太の事業体に変化しつつあると感じています。
2025 年3月期の数値目標は未達の結果となりましたが、収益機会の阻害要因に向き合い、中計目標をやり切るため、今期、主要施策の見直しと新たなKPIを追加しました。
来期以降の数値目標は「中期経営計画2026」策定時に掲げた通り、2026 年3月期の事業利益は540 億円、2027 年3月期は610億円としています。

事業利益実績/計画


ニッポンハムグループが今後も成長し続けるためには、まず我々の存在意義と社会からの求めに立ち返る必要があります。当社グループは、現在、国内の食肉販売量のシェア約20%、日本人のたんぱく質摂取量約6%(当社試算)を供給しています。畜産という一次産業を担い、食のインフラに影響力がある当社グループは、過去より良質なたんぱく質を提供し続けることで企業価値を高めてきました。また、2030 年のありたい姿に向けてVision2030「たんぱく質を、もっと自由に。」を掲げた当社グループですが、その実現に向けて、今中計では「たんぱく質の価値を共に創る企業へ」をテーマに変革を図っています。環境が大きく変わる中、たんぱく質の新たな価値創造に挑戦し続けることが「あるべき姿」であり、さらなる企業価値向上につながると考えているからです。
しかしながら、国内マーケットが縮小していく現在、従来のビジネスモデルを維持するだけでは、当社グループの事業も縮小してしまいます。たんぱく質を提供し続け、さらなる成長を遂げるには既存ビジネスの延長ではなく、新たな戦略構築が急務と考えています。
5つの事業の柱で安定した事業基盤を構築
JA全農との共創に関しては、トップ同士による進捗確認のための会議を定期的に開催しています。2026年度には具体的な数値目標を開示できるよう、現在準備を進めている段階です。この取り組みにより、共創プロジェクトの進展をより一層明確にしていくことを目指しています。
2024年度からスタートしたJA全農やCharoen Pokphand Foods(チャロン・ポカパン・フーズ)社との共創プロジェクトにも引き続き取り組んでいきます。
また、既存事業のバリューチェーンの目詰まりを解消させることも急務です。2025年度は、Step1として海外事業本部を加工事業本部と食肉事業本部に移管しました。2030年には食肉と加工の二つの事業をベースに、海外事業の売上拡大と利益向上を目指します。
さらに現在のボールパーク事業をより進化させ、エンタメ事業として一つの柱にしつつ、新しい柱として新規事業を加える構想です。食肉、加工、海外、エンタメ、新規の5つの柱で展開することで外部環境に左右されない安定した事業基盤の構築を実現します。

R&D戦略「プロテイノベーション」で研究開発を加速
2025年6月、たんぱく質をベースとした研究開発の加速を目的にR&D戦略「Proteinnovation(プロテイノベーション)」を策定しました。これは「protein(たんぱく質)」と「innovation(革新)」を組み合わせた造語です。
当社グループが創業以来向き合ってきたたんぱく質は、まだ多くの未知の可能性を秘めています。お客様ニーズや社会課題の解決につながる研究開発を「既存事業の進化」と「新規事業の創出」の二つテーマで取り組みます。具体的には、「既存事業の進化」において、生産DXや新たんぱく等の領域に、「新規事業の創出」では、畜産副産物を活用した医療系や化粧品系の製品・サービス展開を進めていきます。既存事業の進化においては比較的早い段階で成果につなげていきたいと考えています。
企業価値の向上には、財務戦略や資本政策が不可欠です。スピード感を持って企業価値向上に向けた戦略立案を図るため、キャリア採用で入社した大西 淳氏を役員に据え、VBM推進室を新設しました。当社の役員は事業を経験した社員が多く、固定観念にとらわれることがあるため、外部から新しい視点や知識を取り入れることが重要です。これにより、当社グループがより良く発展していくことを期待しています。
経営のスピードを上げ、危機を成長のチャンスに
私は、当社グループの長期的な成長を見据え、改革を推進するために執行役員の若返りを図りました。特に、変革が求められる食肉事業本部では、6名の役員のうち4名を新たに任命しました。また、グループ会社においても、50代の幹部を社長に任命し、新たなリーダーシップのもとで改革を進めています。日本ピュアフード(株)では、新社長が自らの挑戦を通じて売上収益を伸ばし、具体的な成果を上げることに成功しました。
ここ数年、為替や関税、想像以上のインフレなど、驚くような変化が生じています。想定以上のスピードで環境が激変する中、我々が過去と同じスピードで対応していては変化に対応できません。

実績数値をベースに単年のPLを意識するだけでなく、「あるべき姿」からバックキャスト思考で考え、非連続の成長に向けた「挑戦」をしていく必要があります。現場への挑戦意欲の浸透に向けて、私は1年間現場を巡り、さまざまな方と議論しました。2024年度は、「変えてもええで。」というスローガンをつくり、リアルでの対話とイントラネット等での啓発活動を展開しましたが、挑戦する姿勢が見受けられるようになってきたと思う一方で、「挑戦」する意識が自分ゴトとして現場に浸透していないと感じることもあります。今期は一歩進んで、「もっと変わらなあかん‼」にスローガンを変更しました。激変する外部環境に対応できる強靭な企業体への変革ができれば、飛躍的な成長が可能です。
また、現場まで挑戦の意識を浸透させるには、ミドルマネージャーの育成・強化が鍵だと考えています。会社の方針をミドルマネージャーが理解し、自分の言葉で現場の社員に伝え、行動を変化させることで挑戦する風土へとつながっていきます。そのために、マネジメント体制や評価も見直しました。私自身も現場とのコミュニケーションを継続し、挑戦する意識が浸透するまで何度でも伝え続ける覚悟でいます。
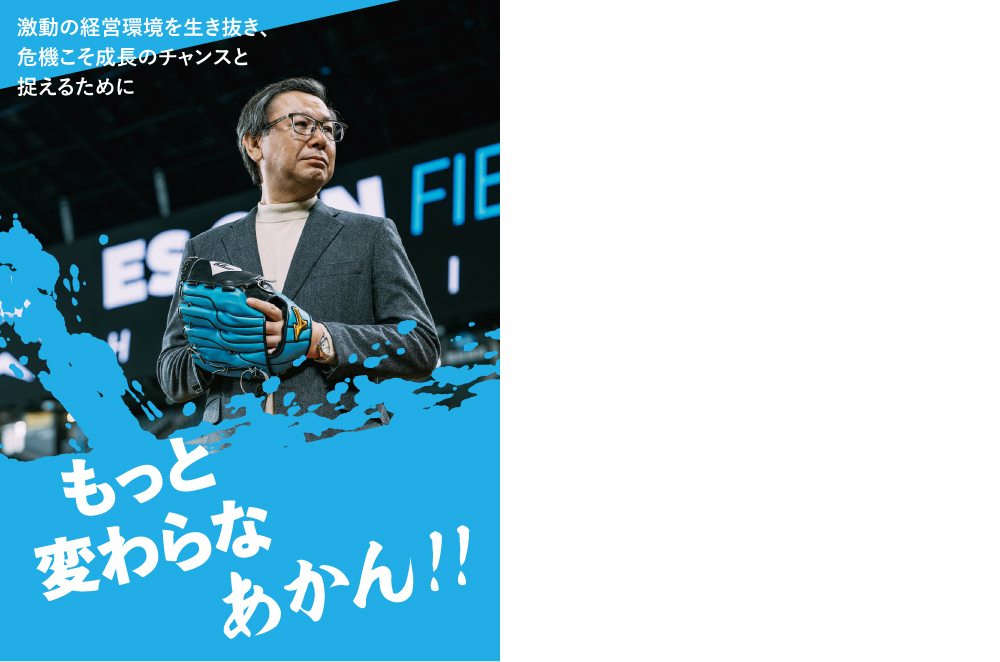
経営トップとして次世代の育成に注力

挑戦する組織風土の醸成に向けて、引き続き「変革型経営人財の育成・獲得」と「多様な人財の活躍推進」の二つのテーマで人財戦略を進めます。
特に「変革型経営人財の育成・獲得」が重要なテーマであると私は考えています。現経営陣を育成することもですが、次世代の役員育成も重視しなければなりません。10 年、20 年後のニッポンハムグループの中心になるのは、その世代だからです。次世代育成を考えた際の現在の課題は自分の育った部門しか分からない状態であることです。そこで、変革型経営人財の育成を目的に、グループ会社や各事業部の責任者を対象とした経営セミナーを定期的に開催しています。今年は私自らが経営者としての心構えについて講話し、事業部の垣根を超えて、バックキャスト思考で仕事に取り組んでほしいことを伝えました。次世代役員には将来を見据え変革に挑戦してもらいたいと思います。
当社グループは本来、変化を恐れず挑戦し成長を遂げた企業でしたが、2002 年以降、コンプライアンスの強化を徹底してきた結果、組織が硬直化しているように感じています。昨今の急激な環境変化を踏まえると、人財や組織の変革が急務です。次世代の経営を担う人財育成は私自身の責務ですので、私が持っている経験や知識等、伝えられるものはできる限り伝えていきたいと思っています。
また、従業員のモチベーション向上を狙うと同時に挑戦する風土醸成につなげるために、これまでの優良事業所表彰を「NHGAward」と名称を改め、表彰式などの内容も大きく変えました。素晴らしい活動や業績をあげた組織の従業員一人ひとりの頑張りを称え、その労いとしてふさわしい表彰を行い、また次なる挑戦を促す機会としています。
「多様な人財の活躍推進」については、働きがいを持って仕事に挑戦してもらうため、「コンプライアンス推進活動」を「働きがい推進活動」に名称を改めました。コンプライアンスを重視する企業風土はすでに根付いています。今以上に従業員一人ひとりが挑戦に向け、能力を最大限発揮できるように、働きがいのある職場創造を継続してまいります。

当社グループらしいサステナビリティ戦略を推進
企業経営においてサステナビリティの取り組みの重要性はますます高まっています。当社グループは「食べる喜びの提供」「新たな価値の創出」「地球環境の保全」「レジリエントな事業基盤の強化」の4つの柱からなるサステナビリティ戦略を定めて取り組んでいます。
今後は特に、たんぱく質の供給メーカーとして当社グループらしいサステナビリティ活動に注力していきたいと考えています。さらに、たんぱく質を供給することで、新しい食の未来にも貢献していきたいと考えています。例えば、「シャウエッセン®」は日本に浸透していなかったあらびきウインナーを浸透させ、新しい食文化を創造しましたが、今後はより多くの人に食べていただけるよう、無添加のおいしい「シャウエッセン®」をつくる、それが私個人の夢でもあります。
北海道北広島市では、年に1回「シャウエッセン®」を給食で提供し、食育というかたちで地域社会への貢献に取り組んでいます。このほか、カーボンニュートラル農場の実現に向けて、北海道南幌町の土地に太陽光発電を設置し、北海道内の自社養豚場への電力供給を始めています。
事業活動を通じてサステナビリティに優れている活動をした従業員やプロジェクトに対して表彰する社内表彰制度等を継続し、サステナビリティ活動を現場に定着させていきます。今後も社会課題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
困難や壁を乗り越え、たんぱく質の価値を共に創る企業へ
「構造改革」「成長戦略」「風土改革」の三位一体の全社戦略はぶれずに行っていきます。
「中期経営計画2026」を策定する際に、2027 年3月期の事業利益610 億円からのギャップを算出し、構造改革で100 億円、成長戦略で60億円の利益獲得数字を設定しました。計画している数字がぶれてくるようであれば、施策を見直し、それがうまくいかなかったとしてもまた次の施策に取り組む―積み上げ方式ではなく、バックキャスト思考で何度も何度も挑戦し続けることが今中計、そして次期中計の790億円以上を達成する鍵だと考えています。
ステークホルダーの皆様には、引き続きご支援お願い申し上げます。

- ホーム
- IR情報
- IRライブラリー
- 統合報告書/アニュアルレポート
- 統合報告書2025年度版
- 社長メッセージ

